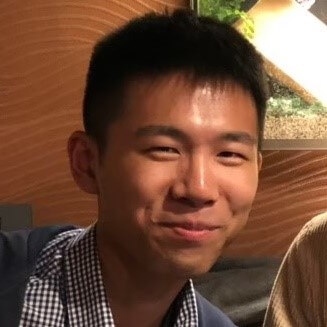【赤本等】大学入試過去問、効果抜群の使い方
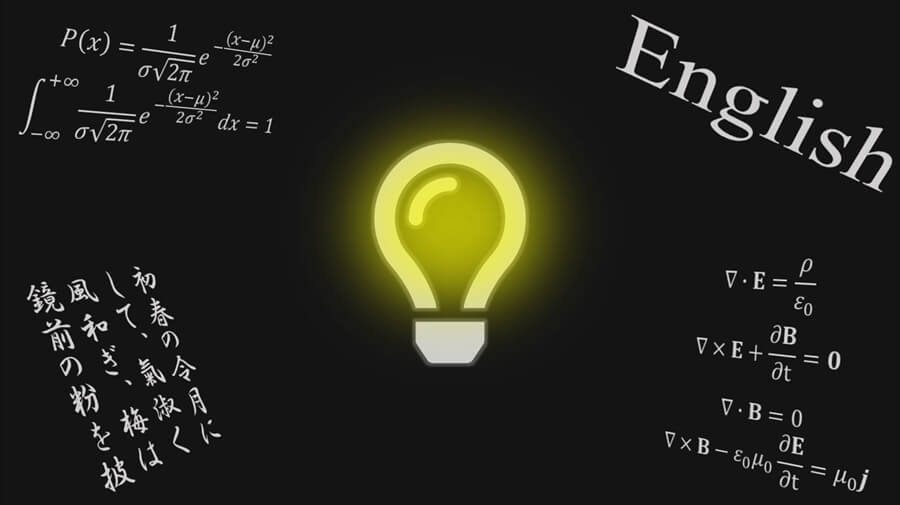
お読みいただいてありがとうございます、東大大学院1年の吉田です。
今回は、過去問を使った勉強法についてまとめていきます。
過去問は、受験生の多くが使うツールではないでしょうか。
けれども、なんとなく問題を解くだけになっている人も、多いのではないかと思います。
漫然と解くだけでは、過去問をフル活用できているとは言えません。
ここでは、過去問をこなす意味、そしてどういう使い方が効果的か、という点について、お伝えしていきましょう。
大学入試過去問を解く4つの意味

さて、過去問を解くことには、主に4つの意味があると思います。
それは、以下の通りです。
-
出題傾向をつかむ
-
出題形式に慣れる
-
実力の目安
-
問題集として使う
順番にお話ししていきましょう。
出題傾向をつかむ
過去問に触れることで、問題の傾向をつかむことができます。
自分の志望校が、どういう問題を出すのか。
あるいは、共通テストでどのような形式で問題が作られるのか。
時間は十分にありそうか、それとも、全部を解ける受験生はいないくらいの分量なのか。
実際に解いてみることで、こういったことを肌感覚で理解できるでしょう。
それをもとにして、今後の対策を練ることができます。
出題形式に慣れる
何年分か過去問を解いていくと、問題の形式に慣れることができます。
これは特に、二次試験の問題について、大きな意味をもつと思います。
なぜなら、大学が独自に作る入試問題には、その大学のカラーが色濃く出やすいからです。
たとえば英語で、超長文が出題されるのか、難しい和訳が求められるのか、クリエイティブな英作文が要求されるのか、問題を解くスピードが大切になるのか、…。
数学は、スピードが大事なのか、それとも、少ない問題数で思考力を試されるのか。
こういったことは、各大学によって、全然違います。
そういった、ある意味独特な問題の形式に慣れていけるというのが、過去問を解く意味の1つです。
実力の目安
過去問を解いて採点することで、今の実力を測ることができる、という側面もあります。
過去の合格者最低点や平均点と自分の点数を比べることで、実力を確かめられるわけです。
もし合格者の点数がきっちりわからなくても、だいたい7割取れれば安心とか、そういった目安をもとに、自分の現在地を知ることができるでしょう。
問題集として使う
実は過去問は、良質な問題集です。
もしかしたら、こういう見方をしたことがあまりない方も多いかもしれません。
共通テストにしても二次試験にしても、入試問題は、時間と手間をかけて、じっくり練って作られています。
ですから、そこには、良問がたくさん詰まっているのです。
そういう意味で、過去問を解いていくうちに、どんどん実力が上がるケースはよくあります。
うれしいことに、「共通テストの過去問をずっとやっていたら二次の点数も上がっていた」ということも起こりえるわけです。
この「過去問を問題集として使う」ということについては、また別の記事で詳しく書こうと思います。
さて、ここまで、過去問を使う4つの意味についてお話ししてきました。
これを踏まえて、過去問の効果的な活用法を次にご紹介しましょう。
大学入試過去問の活用法

僕がおすすめする使い方は、次の通りです。
-
ある程度学習が進んだら、最初に1~3年分くらい解いて、傾向をつかむ
-
ほかの参考書などで対策をする
-
過去問をどんどん解いて演習を積む
まずは、教科書の勉強がある程度終わってきたら、少し過去問を解いてみるといいでしょう。
どんな問題が出るのか、どういう力が求められるのか、といったことを把握できます。
この「勉強が進んできたら」という点がミソです。
なぜなら、あまりに未習範囲が多い状態で手をつけても、問題がどれくらい難しいものなのかがわからないからです。
これは習っていないから解けないのか、それとも、習っていても解くのが大変な問題なのか、という区別がつかないわけです。
さて、そうして傾向をつかむことができたら、いったん過去問から離れて勉強するのがいいと思います。
理由は単純で、過去問がもったいないからです。
手に入る過去問は、せいぜい数年分~10年分といったところではないでしょうか。
だから、過去問でなくてもできる勉強には、なるべくそれを使わないのが無難だと思います。
一般的な勉強法としては、問題集で苦手な分野をつぶす、というのがあるでしょう。
ほかにも、予備校が作った模試をまとめた問題集(駿台の青本や、河合塾の黒本など)で勉強する手もありです。
そうして対策を積むことができたら、いよいよ過去問を使って勉強を進めていくのが良いと思います。
始めは時間をきっちり測る必要はないんじゃないかと思います。
慣れてきたら、本番通りの時間で解いて、時間配分も練習していくと良いでしょう。
そして、解いた後は、しっかり復習をすることも大切です。
分からなかった英単語を辞書で調べる、数学で確率の問題が解けなかったら、もう一度問題集に戻って確率の分野を全部解く、…。
そういうふうにして、過去問を解いた何倍もの時間を復習に割くことで、実力は着実に伸びていきます。
では最後に、Q&A形式で、細かいところを補足していこうと思います。
よくある/あまりない質問

過去問(赤本)は、いつ買えばいいですか?
なるべく早く買うのがおすすめです。
なぜなら、売り切れの心配があるからです。
実は過去問は、普通の本や参考書と違って、売り切れ(入手不可能)になる可能性が高いという特徴があります。
過去問集は、毎年新しいものが出ますよね。
だから、「売り切れたらもう今年版は終わり。来年また新しいのを売り出せばいいから」とされてしまいやすいんです。
ですので、志望校がある程度固まったら、早めに買っておくのがおすすめです。
過去問は、新しいものから解いた方がいいですか?
はい、新しいものから、順番に進むのがいいでしょう。
なぜなら、古いものは、今と出題傾向が違う可能性があるからです。
直近の何年分は、直前期に残しておいた方がいいですか?
そこまで神経質になる必要はないんじゃないかと個人的には思いますが、残せるものなら、残しておくのが無難かもしれませんね。
そうして、それを直前期に時間を測って解くことで、本番の予行練習になると思います。
まとめ
以上、過去問の使い方について、詳しくお話してきました。
まとめておくと、過去問を解く4つの意味は、
-
出題傾向をつかむ
-
出題形式に慣れる
-
実力の目安
-
問題集として使う
おすすめの勉強法は、
-
ある程度学習が進んだら、最初に1~3年分くらい解いて、傾向をつかむ
-
ほかの参考書などで対策をする
-
過去問をどんどん解いて演習を積む
です!
ただ順番に解いていって満足するのではなく、しっかりやる意味を考えながら、勉強を進めていきたいですね。
もちろんここに書いた勉強法がすべてではありません。
ご自身の学習状況や、学校の対応などを総合して考えて、いろいろ工夫を加えることがおすすめです!
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
書き下ろしメールマガジン
Studiumメールマガジンでは、新着記事のお知らせや、会員限定コラムの配信などを行っています。
よかったら一度、登録してみてください!
Studiumと一緒に受験を走り抜けてみませんか?
東大院生が”受験の極意”を体系化!
このブログの全記事を執筆する吉田が、電子書籍を出版しました!
タイトルは、『受験生活を颯爽と走り抜けるための7つの知恵』。
多くの受験生に読んでいただけるよう、無料に設定してあります。
興味がある方は、ぜひ手に取ってみてくださいね。