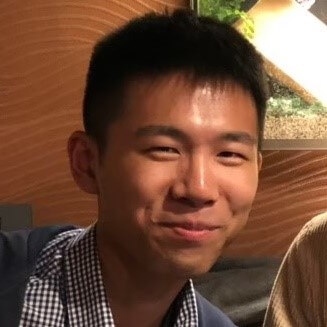【意外】勉強の動機の良い・悪い【診断付】
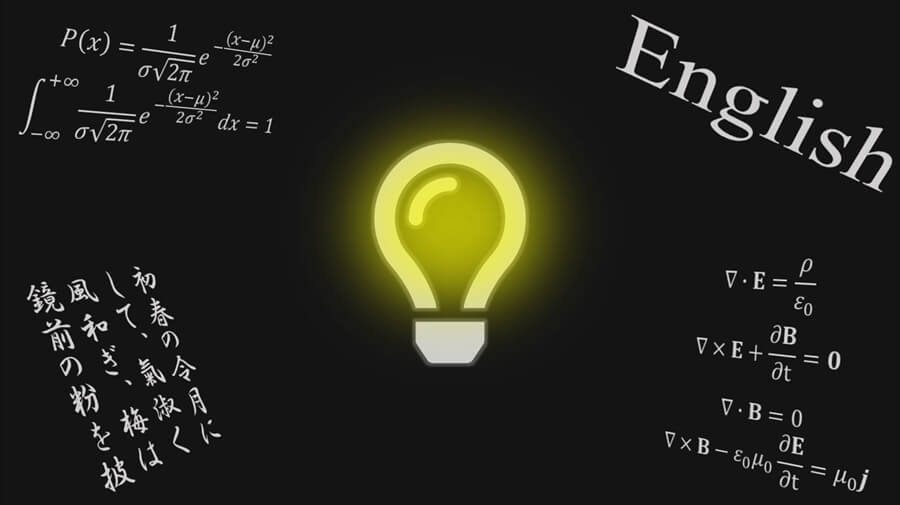
今回は、勉強の動機、目標には良いものと悪いものがある、という話をしていきます。
「目標の種類」と言われても、恐らく「何それ?」ではないでしょうか。
学校でもあまり教わることは無いと思います。
しかしこれを知らずに過ごしていると、知らないうちに心理の罠にはまってしまうかもしれません。
成績を上げていくうえで重要な思考法を解説していきます。
目標の種類

まず、目標には大きく分けて3種類のものがあるという話をします。
その3種類とは、以下の3つ。
- 習得目標
自分の能力を伸ばすために行動する - 遂行目標
自分の能力に対する評価のために行動する- 遂行接近目標:能力の高さを証明するため
- 遂行回避目標:能力の欠如を隠すため
人によって、この3つのうちどんな目標を立てがちかというのが決まってきます。
しかしこの説明だけ読んでも、いまいちピンとこないでしょう。
そこで、自分はどのタイプなのかを診断できるテストを用意しましたので、ぜひやってみてください。
テストの後に、詳しく説明していきます。
タイプ診断テスト

次の15の質問にお答えください。
※ページが長くなるのを防ぐため、テストは折りたたんでいます。文字をクリックしてお開きください(ブラウザによっては初めから展開されているかもしれません)。
テストはこちら
いかがだったでしょうか。
一番点数の高いものはどれでしたか?それを覚えておいてください。
ここから、タイプ別の特徴について詳しく説明していきます。
タイプ別詳細

※自分のタイプの箇所だけでなく、すべてを読むことでこの後の話の理解が深まります。ご自分のタイプ以外も一読いただくと良いかと思います。
A得点が高い人
A得点が高い人は、習得目標をもつ傾向にあります。
上のテストで、A得点に加算される質問は
- 1. 学校の授業からはできるだけ多くのことを学びたいと思う。
- 5. 授業の内容をできるだけ徹底的に理解することは重要だ。
- 9. 学期を終えるとき、より広く深い知識を得ていたいと思う。
- 13. 授業で使う教材を完璧にマスターしたいと思う。
- 14. 授業では、難解な内容であっても、好奇心が刺激される教材を好む。
の5つです。
これらに「あてはまる」と答えると、A得点が高く出るようになっています。
習得目標をもつとは、自分の能力を高めたいから行動する、ということでした。
つまり、英語を話せるようになりたいから英会話を勉強する、ホームランを打てるようになりたいから毎日素振りをする、といった考え方で行動します。
このタイプの人は、失敗に強く、高い壁にも積極的に立ち向かう傾向にあります。
むしろ「失敗は成功のもと」と考えて前向きに進んでいきます。
研究者に多いタイプと言えるでしょう。
B得点が高い人
B得点が高い人は、遂行接近目標をもつ傾向にあります。
上のテストで、B得点に加算される質問は
- 2. 他の人と比べて良い成績を取ることは重要だ。
- 4. 授業で他の人よりも成績を取ろうと思うとやる気が出る。
- 6. テストでは、他の人よりも良い点を取りたいと思う。
- 8. 授業で他の人と比べて成績が良いならば、よくやったという気持ちになる。
- 10. 自分の能力を友人や先生や家族などに示すために、テストでは良い点数を取りたい。
の5つです。
これらに「あてはまる」と答えると、B得点が高く出るようになっています。
遂行接近目標をもつとは、自分の能力の高さを証明するために行動する、ということでした。
つまり、自分は英語が話せるんだと思いたいから英会話を勉強する、チームメイトに「あいつのバッティングはすごいよな」と思われたいから毎日素振りをする、といった考え方で行動します。
このタイプの人は、能力の高さを示したいので猛烈に頑張ることができます。
「自分の能力は努力でいくらでも高められる」と考えて、その高さをアピールするために、努力で実際に高めてみせるのですね。
高学歴の人に多いタイプとも言われています。
C得点が高い人
C得点が高い人は、遂行回避目標をもつ傾向にあります。
上のテストで、B得点に加算される質問は
- 3. 他の人よりも悪い点数を取ってしまうのではないかと心配だ。
- 7. もし授業中につまらない質問をしたら、頭が良くないと思われるのではないかと心配だ。
- 11. 勉強する大きな理由は、恥をかかないようにするためだ。
- 12. 授業中に間違った答えを言ったら、他の人が自分のことをどのように考えるか心配だ。
- 15. 他の人に出来が悪いと思われないようにするために勉強する。
の5つです。
これらに「あてはまる」と答えると、C得点が高く出るようになっています。
遂行回避目標をもつとは、自分の能力の欠如を隠すために行動する、ということでした。
つまり、外国に行って「あいつは英語も話せやしない」と思われたくないから英会話を勉強する、試合で恥をかきたくないから毎日素振りをする、といった考え方で行動します。
このタイプの人は、能力の低さを周りにさらすことを非常に恐れています。
それがさらに進んで、あえて真面目に取り組まないなど、失敗してもよくなる保険をかけたりすることもあります。
それによって無気力になってしまうといったこともあり得ます。
以上、3つのタイプについて解説してきました。
何となく、習得目標(能力の向上を目指す)が最高で、遂行回避目標(無能と思われたくない)が悪いことのように思えるかもしれません。
しかしこれは人それぞれで、どれが良くてどれが悪いと一概に言えるものではありません。
ただし、何かに失敗したときは、これらの裏に潜む心理が重要になってきて、遂行回避目標をもっているとややまずいかもしれません。
前置きがだいぶ長くなりましたが、ここが、今回の話の本題です。
重要なので節を分けて書きたいと思います。
原因帰属
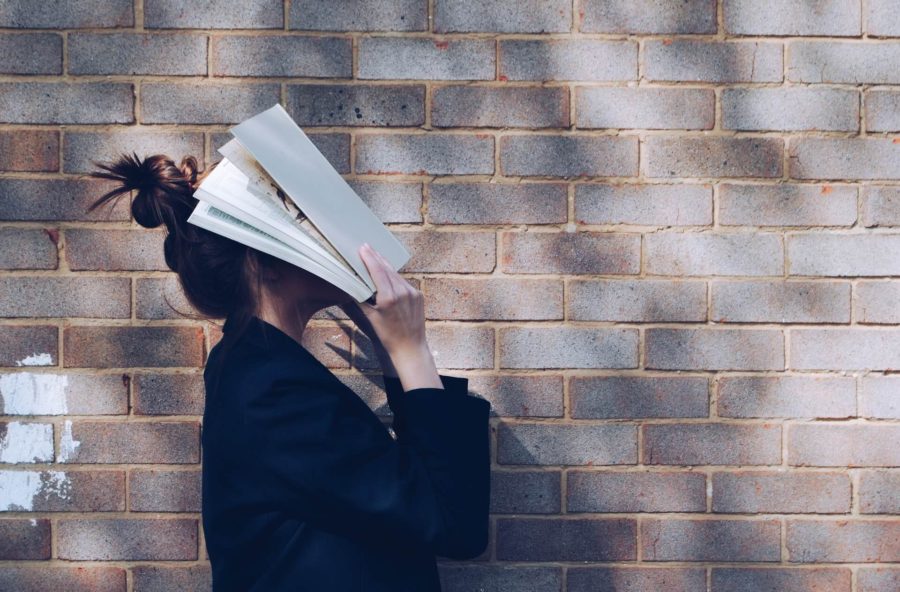
なぜ、失敗したときに遂行回避目標をもっているとまずいのか。
一言で言うと、それは「失敗を能力のせいにして、努力しなくなる可能性があるから」です。
つまり、例えばテストで悪い点を取ったときに、「どうせ私はバカだから」と言って勉強しなくなってしまうということです。
もう少し詳しくお話しします。
「遂行目標」というくくりで考えると、これは「能力を示そうとする目標」でした。
それがどうして「接近型」(有能だと思われたい)と「回避型」(無能だと思われたくない)に分かれるのでしょうか。
その根底には、
- 能力観
- 自己効力感
この2つが絡んできます。
※自己効力感とは、「自分はやればできる」とどれだけ思っているか、ということです。
つまり、能力観では
- 能力は努力で変わると考える→接近型
- 能力は何をしても変わらないと考える→回避型
という分岐が起き、自己効力感では
- 自己効力感が高い→接近型で、努力する
- 自己効力感が低い→回避型で、努力から逃げる
と別れます。
要するに、接近回避目標をもつ人というのは、「能力なんて変わるもんじゃないし、私は何をやったってうまくいかない。だけど無能だとは思われたくないから、テスト勉強でもしてそれなりの点数を取ろうかな」と考えがちということです。
そして、失敗の原因を、努力ではなく能力のせいにします。
こうなると、自分の思考によって、どんどん努力しない方向に引きずられて行ってしまいます。
みなさんの周りに、こんな人はいませんか?
テストの日に、「いやー昨日遅くまでYouTube観ちゃったよ、勉強もしないで」と自慢げに語ってくるクラスメイト。
そういう人に限って、普段YouTubeの話なんてしないんですよね(笑)。
どうやらテストの前日にだけYouTubeやゲームにハマるようです。
話が逸れました。
これは何の例として出したかと言うと、能力の低さを隠す例です。
「昨日YouTubeを観た」と言えば、仮にテストの点が悪かったとしても、それは彼の頭が悪いというよりは「YouTubeを観て勉強しなかったせい」になりますよね。
つまり、遂行回避目標(頭が悪いと思われたくない)をもち、なおかつ努力する気を失った例です。
まとめると、遂行回避目標をもっても良いのですが、それで失敗したときに、「失敗は努力でなくて能力のせいだ」「能力は努力で変わらない」と考えてしまうことは危険だということです。
そして遂行回避目標をもつ人というのはそういう心理が裏に潜んでいがちだから気をつけなければならない、という話です。
失敗したときは、「どうせできない」ではなく「努力が足りなかった」と考えることが大切です。
まとめ
以上、動機の種類、そしてその裏の心理についてお話ししてきました。
少し難しい話だったかもしれません。
ですが要するに、全ての原因を自分の「努力」と考えましょうという結論です。
この思考法をもとに、受験生のみなさんは、ぜひ成績を今よりもっと上げるために頑張ってください!
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
書き下ろしメールマガジン
Studiumメールマガジンでは、新着記事のお知らせや、会員限定コラムの配信などを行っています。
よかったら一度、登録してみてください!
Studiumと一緒に受験を走り抜けてみませんか?
東大院生が”受験の極意”を体系化!
このブログの全記事を執筆する吉田が、電子書籍を出版しました!
タイトルは、『受験生活を颯爽と走り抜けるための7つの知恵』。
多くの受験生に読んでいただけるよう、無料に設定してあります。
興味がある方は、ぜひ手に取ってみてくださいね。