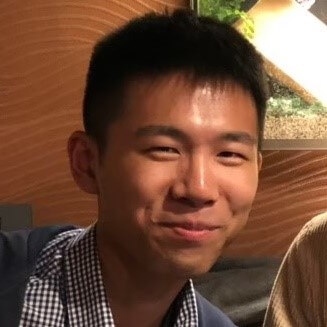【フル活用】模試、復習だけで終わっていませんか?
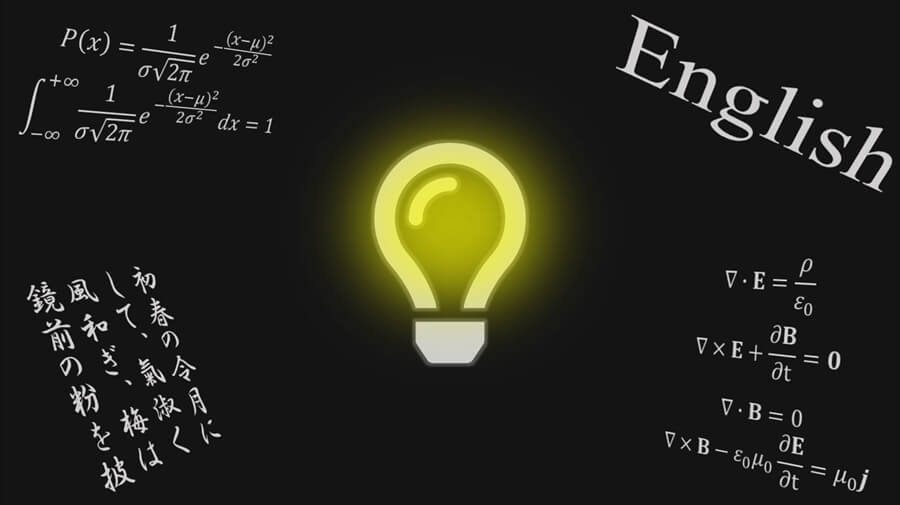
受験の必須アイテムの一つが、模試。
よくある例えですが、日々の勉強が練習だとしたら、模試は練習試合。
日頃の勉強の成果を試したり、合格可能性の判定を得たりするのに最適な機会と言えるでしょう。
ところで、みなさんはその模試をフル活用できていると思いますか?
模試を受けた後、復習するだけで終わっていませんか?
「学校の先生からは『復習しなさい』としか言われていない」「他に何をやればいいの?」
今回は、周りにグッと差をつけることができる模試の活用法を紹介しましょう。
なお、主に高3生を想定して書いていますが、高1生、高2生の方も知っておいて損は無い内容です。
そもそも模試は何のため?
まず、そもそも模試は何のために受けるのかというのを整理してみましょう。
力試し、志望校の判定が欲しいから、などの目的が思い浮かぶと思いますが、私が大切にしてほしい観点は「弱点発見」です。
たしかに模試には、全国順位を競ったり志望校判定を得られたりするという側面もあるのですが、それよりも目を向けてほしいのは、模試を受けた後です。
つまり、模試をその後の勉強のコンパスや起爆剤にしてほしいということです。
これまで勉強してきたことを実戦形式で試してみて、自分に何が足りないのかをあぶりだし、その後の勉強の指針を得ることがとても大切です。
こう考えると、復習だけでなく、やることが見えてきませんか?
模試の後は勉強計画を立てるべし
そう、模試の後は、今後の勉強計画を立てることが必要です。
模試で見つかった弱点を入試までに克服していくことが「受験勉強」ですよね?(もちろん教科書で未修の範囲がある場合はその勉強もですが)
そのスケジュールを組み立てるわけです。
以下のような手順に従うとスムーズに進むと思います。
- 課題を2つ又は3つ挙げる(多くても取り敢えずは3つに絞ります)。
- それらに優先順位(=解決しなければいけない順位)をつける。
- それらを克服するための勉強法を決める(教材、やり方、進め方など)。
- 1週間を単位にしてスケジュールを立てる。
このようにして、この先3か月程度の計画を立てることがおすすめです。
参考までに、私が受験生時代に立てた、高3の10月~12月のスケジュールを載せておきます。
自分で分かれば良いので参考書名などはかなり省略して書いていますが、「計画ってこんな感じ」という雰囲気だけつかんでもらえたらと思います。

例えば数学は、確率が一番の課題として挙がっていて、まずは一度復習した東大模試の復習を再度すること、そして以前に使っていた参考書でもう一度基礎を固めること、を10月にやろうとしていますね。
物理が途中で切れているのは、学校が今後どのような体制で受験をサポートしてくれるかがこの時点では不明だったからです。
このように、分からない部分は未定でも良いと思います。
私の場合、取り敢えずの課題は熱力学で、それは10月に克服する見通しが立っていたので。
そしてこの計画、模試を受けるたびに見直し・修正もしたいです。
例えば、確率を10月で克服する計画を立てていて、しかし11月に模試を受けてみたらまだ確率が解けなかった。
この場合はもう一度確率を勉強するよう計画の修正が必要かもしれません。
あるいは、新たな大きい課題が見つかって、その克服に急いで取り掛からなければならないかもしれません。
このように見直し・修正も心がけていって、常に合格への最短ルートを歩めるように意識したいところです。
まとめ
以上、模試後の計画の必要性・立て方をお話ししてきました。
一度の模試から今後の勉強計画まで立てられたら、とてもお得だと思いませんか?
ぜひ直近の模試を引っ張り出してきて、上に書いた手順で計画を立ててみてください。
志望校への距離がグッと縮まるはずです。
最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。
書き下ろしメールマガジン
Studiumメールマガジンでは、新着記事のお知らせや、会員限定コラムの配信などを行っています。
よかったら一度、登録してみてください!
Studiumと一緒に受験を走り抜けてみませんか?
東大院生が”受験の極意”を体系化!
このブログの全記事を執筆する吉田が、電子書籍を出版しました!
タイトルは、『受験生活を颯爽と走り抜けるための7つの知恵』。
多くの受験生に読んでいただけるよう、無料に設定してあります。
興味がある方は、ぜひ手に取ってみてくださいね。